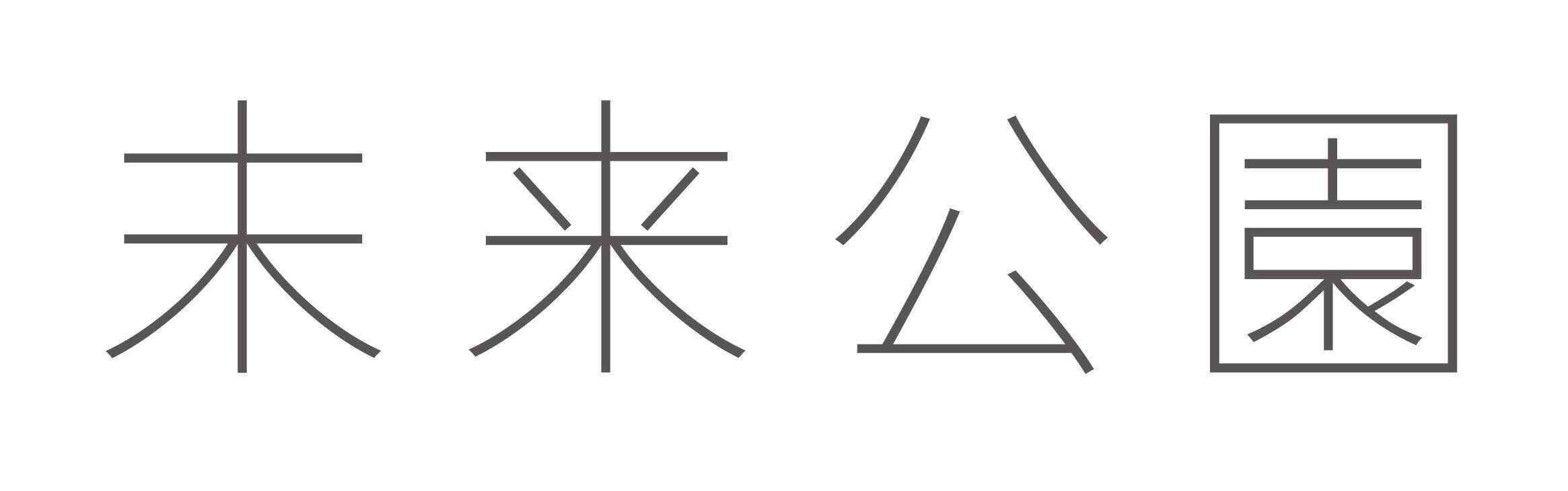最初のステップ「共感」は、「ユーザーを把握する」とか「ユーザーを知る」
という意味でもありますが、なぜ「共感」という言葉を使うのでしょうか?
実は、ここが大切なんです。
把握→つかむとか、理解すること。
知る→こちらもつかむこと。
(かんたんにまとめてます)
これらは、問題解決の材料として、表面的な行動を情報として集めた。。
というようなニュアンスなのかな。。と思います。
共感→気持ちとして感づる。同感。
デザイン思考は「人間中心デザイン」とも言います。
いかに、人間中心で考えることができるか?
内面の心の部分まで入り込むことができるか。
ユーザーの表面的な回答だけでなく、潜在的なニーズまでもつかむことがポイントになっているという意味だと思います。
潜在的→本質的なニーズをつかむことで、破壊的なイノベーションにつなげることができるようになるのです。
例えば、輸送手段が馬から自動車に変わった時代で例えてみると。。
<表面的な問題解決の場合>
1、ユーザーの要望
もっと早く走れる馬車が欲しい!
2、問題解決する人の回答
目の前の馬を見て、もっと早そうな馬に乗り換て、馬車を軽くして馬が早く走れるようにしましょう!
3、改善策
もっと早く走れる馬にする、。もっと大きな馬車にする。
4、結果的には、早く、多くの荷物を運べるようになりますが。。
馬であることは変わらないので、馬は病気になったり、休ませたり、気持ちが荒くなる時があったり。。
馬自体の問題は解決できていません。
<共感という思考で問題解決の場合>
ニーズの出発点となるユーザーの要望は同じ
1、ユーザーの要望
もっと早く走れる馬車が欲しい!
2、問題解決すえる人の問い
なぜ、もっと早く走れる馬車が欲しいのですか?
3、ユーザーの回答
運びたい荷物の量も増えるし、運ぶ回数も増えてくるから、効率よく運びたいんだよ。
4、問題解決する人の問い
では、問題の根底は馬ではなく移動手段でより多くの荷物をもっと頻繁に運べるようにしたいのですね。
5、問題解決する人の思考
だったら馬でなくてもよいのでは?もっと、効率的に頻繁に動けるもの馬も疲れちゃうからなぁ。。
馬に変わる、疲れない移動手段とは!
6、改善策
自動車を発明しました。これだったら、燃料さえあれば、もっと早く、もっとたくさんの荷物を
もっと頻繁にはこぶことができます。
表面的な問題解決と共感という思考で問題解決することの違いは?
表面的な問題解決では、馬自体をなんとかしようという思考でした。→ニーズ
共感から導き出した問題解決は、ユーザーの要望をそのまま受け止めないで、その要望の奥底にある本来求めていたことに対して答えることで、自動車というものの発明につながりました。→インサイト
これは、説明するための一例ですが、この考え方を導き出すプロセスの中で実際にいろいろな体験をしてみることも大切です。
実際は、例えば、この時代としたら、実際に馬を使って、移動したり、ものを運んだりしてみる。また、馬から離れて、いろいろな移動手段を見たり体験してみる。
そうすると、馬の本来の目的である移動をもとに、いろいろと置き換えたり、可能性を見つけたりすることができてきます。
これらの作業を繰り返していると、次のステップの「問題提起」につなげるヒントが出てきたりします。
なので、共感から始めることで、改善改良的な問題解決をおこなうのではなく、心の底にある本来求めていることをつかむことで、今までにない新しい提案につなげる考え方なのです。